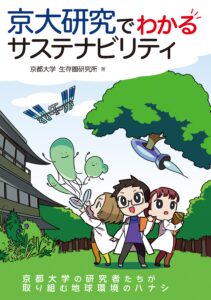生存研の研究者30名が執筆した『京大研究でわかるサステナビリティ』(オーム社)が発売されました
京都大学の附置研究所の一つである生存圏研究所(以下、生存研)は、サステナビリティ(sustainability)科学を標榜する研究組織です。このたび、生存研で行われているサステナビリティ研究の最新の成果を分かりやすくご紹介する、一般向けの書籍『京大研究でわかるサステナビリティ』を上梓いたしました。
『サステナビリティ』というキーワードは、2015年に国連サミットで採択された“持続可能な開発目標”、つまり、“Sustainable Development Goals (SDGs)”の『S』として、社会的に広く知られるようになりました。現在、SDGsへの取り組みは、個人や企業、政府など、さまざまな主体によって行われています。また、SDGsの取り組みや理解には、多角的な視点や多面的な考察が求められることから、非認知能力を育てる探求型学習の主題として、小中高の教育現場でも取り上げられる機会が増えています。生存研ではSDGsが採択される10年以上も前から、サステナビリティの重要性に注目し、サステナビリティを学問的に探究するという世界的にも珍しい取り組みを進めてきました。
この本を通じて、サステナビリティを学問的に探究することの意義を実感していただければ幸いです。一般の方々(おおむね高校生以上を対象)にも気軽にお手に取っていただけるように、難解な専門用語の使用をなるべく控え、イラストや写真を添えた分かりやすい解説を心掛けました。折しも、パリ協定の前身となった京都議定書の発効から20年の節目の今年、ぜひこの本をお手に取っていただき、環境未来都市構想をかかげる古都・京都から発信されるサステナビリティ研究の「おもしろさ」、「むずかしさ」に触れてみてください。
《本著目次》
イントロダクション:「サステナビリティ」を理解するために
第1章 未来の生活を支える新しい材料・エネルギー
未来のクルマは植物からつくる
バイオマスとつくる循環型未来社会
植物バイオマスを材料として使い続けるための接着技術
電子レンジでカンタン、化学反応?
微生物の手も借りたい!植物成分の新たな生産者
第2章 空(そら)から宙(そら)まで広がるサステナブルな空間
レーダーの開発と天気予報の精度向上
「宙」と「空」の境い目
宇宙空間とは、どんなところ?
月での暮らし、地球の暮らしと何が違う?
ミライの電気は宇宙からやって来る!?
宇宙で木を育てる
第3章 環境変動や災害に適応できる社会を目指して
土に空を接ぐ植物の話
微生物コミュニティのパワーを農業に活かす
大好きな食べ物と熱帯林と地球温暖化の知られざる関係?
地震に強い木の家
小さい泡の不思議な力
環境微生物の利用―環境汚染の修復を目指して
第4章 いにしえに学ぶ サステナビリティ
人と木とのつながりを未来へ伝える
日本の伝統文化と植物科学を結ぶ「紫」の糸
木炭―古くて新しい材料のヒミツ
オーロラの記録をさかのぼり、宇宙環境の未来を予測する
木材が過ごした時間を科学で解き明かす
木から森を見て、楽器の音色を未来につなぐ
エピローグ:ミライを拓くサステナビリティ学
【書誌情報】
タイトル:『京大研究でわかるサステナビリティ』
著者:京都大学生存圏研究所 (編集)
出版社:オーム社
ISBN-10: 4274233472
ISBN-13: 978-4274233470
【出版社ホームページ】 https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274233470/