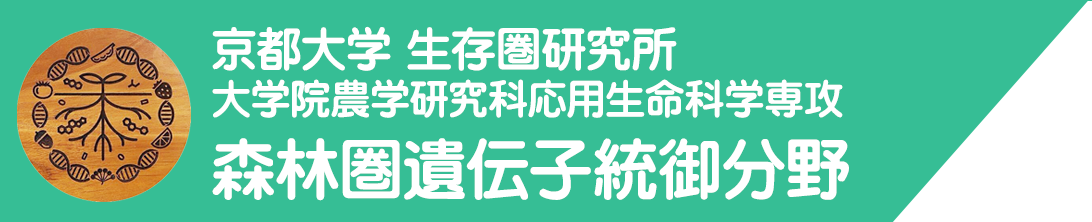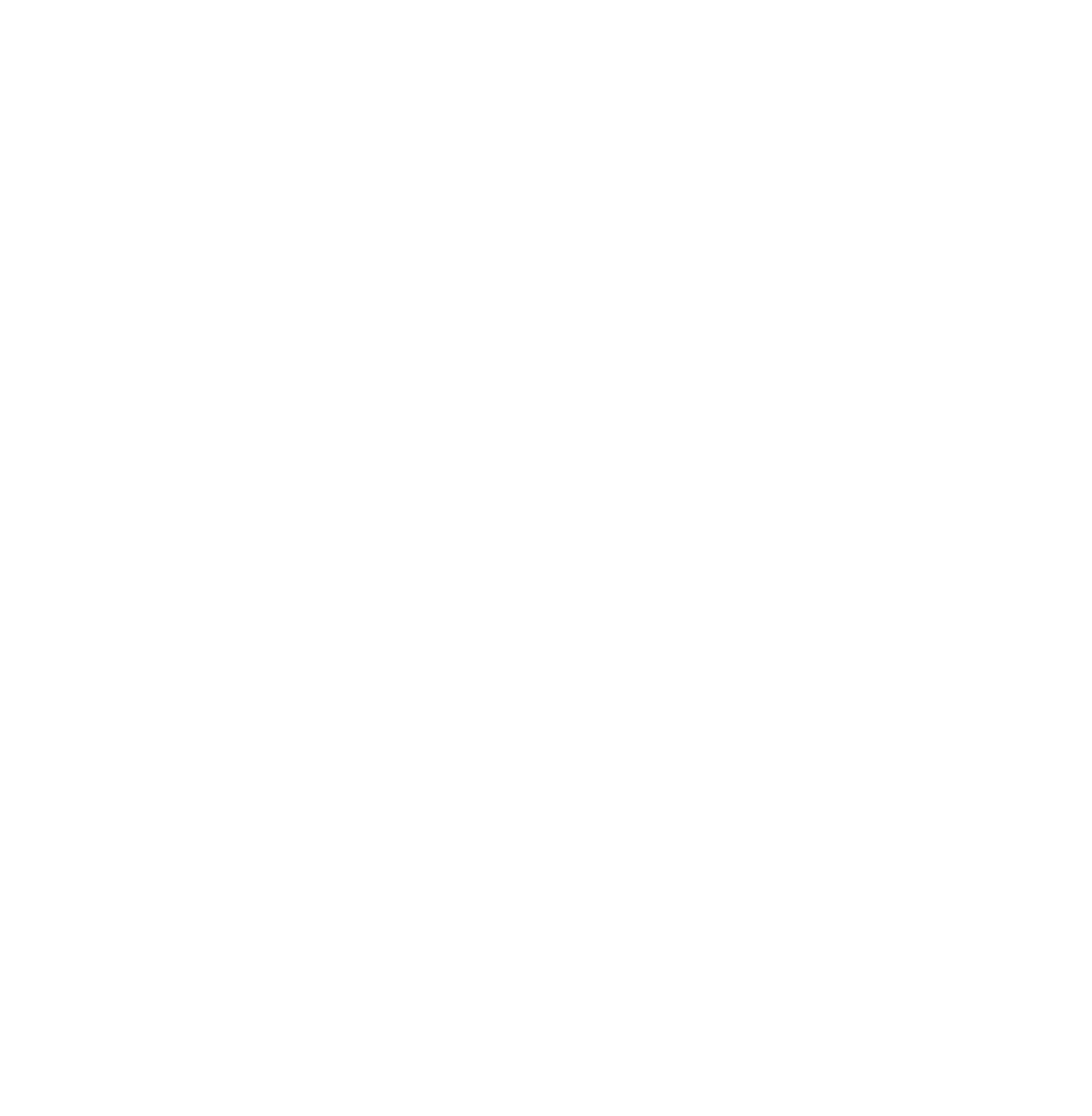矢崎一史プロフィール

E-mail: yazaki.kazufumi.4m
「元々私は薬学出身で、1995年までは薬学の分野に籍を置いていました。薬学を志したのも、元をただせば小学校の頃、テレビで「サスケ」を見ていたら、(日本なのに)川の中でピラニアに追いかけられていたサスケが、懐から黒い薬を出したらすぐにピラニアがやられてしまった、というシーンを見たのが原因であります。その際のナレーションに「当時の忍者は、いざという時のために元気を取り戻せる薬や、敵をやっつけられる毒を薬草から調合できる知識を身に付けていたのだ」というのがありました。スゴイ!と私はすっかりその魅力に取りつかれてしまったわけです。いかんせん、当時は感性豊かな小学生。薬草をやるしかない!!と、完全にカブレまして、以来薬用植物まっしぐらの道にはまってしまったのです。」
最初に薬草ありき、というのがこれまでの人生の出発点だったのは間違いないようです。子どもの頃は、ひたすら山の中を駆け巡って、本の記載のメモと見比べて、後は文字通り五感だけを頼りに、茎は四角とか、根は良い匂いがするとか、噛むと苦いとか・・たくさんの薬草を集めては自分で飲んで試していました。知識が不完全だったので、随分といろんな目にあいましたが・・。薬学部で最初にやった研究が、天然物の単離と構造決定。そのうち植物培養細胞に薬効成分を作らせることを習い、二次代謝産物の生合成の仕事をするようになり、酵素学的研究をやっているうちに「遺伝子の方が早い」と、分子生物の仕事をするようになったわけです。フィールドから天然物有機化学、酵素、物質輸送、遺伝子までやってきた人はあまり多くないのでは?
研究テーマ
- 植物の揮発性有機化合物(BVOC)の生合成と分泌機構(詳しくはこちら)
- 薬用/染料植物ムラサキとシコニンの生合成と細胞外分泌(詳しくはこちら)
- 植物の腺鱗を対象とした代謝系の輸送と蓄積の制御技術
植物の膜輸送体に関する研究(経緯はこちら)
植物二次代謝のプレニル化酵素遺伝子発見の経緯などを短くまとめます。
植物の二次代謝において、フェノール性化合物のプレニル化は、生体機能の維持、生 物活性の上昇、化学構造の多様性、など極めて重要な役割を担う生合成反応です。植 物二次代謝におけるプレニル化酵素遺伝子の最初の発見は、矢崎がまだ助教授時代の 2002年のことでした。当時の学生であった國久さんが、ムラサキからシコニン生合成 の鍵酵素であるLePGT遺伝子を同定してくれたのが一番初めです。その後、少し違っ たファミリーのタンパク質が、フラボノイドのプレニル化酵素であることを見出して くれたのが、私が教授になったばかりの頃の学生だった佐々木さん(2008年)。これ で一気に本酵素ファミリーの研究が広がりました。引き続きその先鋒を担って研究を 大きく発展させてくれたのが、当時学生で今は研究室の助教である棟方くんです。
このテーマは棟方助教に継承しましたので、現在の状況については、そちらのページ を参照してください。植物のプレニル基転移酵素の研究(経緯はこちら)
植物二次代謝系の輸送体遺伝子に関して発見の経緯などを短くまとめます。
ATP結合タンパク質(ABCタンパク質)は、2000年前後にヒトの癌細胞の多剤耐性遺 伝子として盛んに研究されていました。植物にもABCタンパク質遺伝子があることは 知られていましたが、植物における機能はその当時不明でした。矢崎が助教授時代、 植物内在性のアルカロイドを輸送するABCトランスポータを同定したのが2003年のこ とで、植物二次代謝とABCトランスポータを繋いだ最初の業績だったと思います。当 時学生だった士反くんとフランスのCadaracheのForestier博士と共同研究でした。そ の後博士課程から合流してくれた杉山くんを中心にABCトランスポータの研究が発展 しましたが、一方でタバコのニコチンを運ぶのはMATEタイプの輸送体であることを 、ベルギーのGoossens博士らとの共同研究で森田くんが論文にしてくれました (2009年)。
このテーマは杉山教授に継承しましたので、現在の状況については、そちらのページ を参照してください。
研究歴
| 1986年4月 | 岡山大学助手(薬学部・薬用植物園) |
| 1989年8月 | Alexander von Humboldt 財団奨学生として渡独 ボン大学、およびマックスプランク研究所(ケルン)にて研究 |
| 1991年8月 | 岡山大学助手(薬学部・薬用植物園) |
| 1992年5月 | 京都大学助手(薬学部・生薬学講座) |
| 1996年2月 | 京都大学助教授(農学部・農芸化学科・分子細胞育種学講座) |
| 1997年4月 | 京都大学大学院助教授(農学研究科・応用生命科学専攻・分子細胞育種学分野) |
| 1999年4月 | 京都大学大学院助教授(生命科学研究科・統合生命科学専攻・全能性統御機構学分野) |
| 2002年9月 | 京都大学教授(木質科学研究所・遺伝子発現分野) |
| 2004年4月 | 京都大学教授(生存圏研究所・森林圏遺伝子統御分野) |
| 2024年4月 | 京都大学 名誉教授/同学生存圏研究所 特任教授 |
| 現在に至る | |
研究業績
学位
京都大学薬学博士
受賞歴
| 1998年7月23日 | 日本植物細胞分子生物学会(第16回、仙台)奨励賞受賞。 題目「シコニン生合成の発現制御機構の解明」 |
| 2000年9月7日 | 日本生薬学会第47年会(東京)学術奨励賞受賞。 題目「ムラサキ培養細胞におけるシコニン生合成遺伝子の解析とその光応答」 |
| 2002年11月20日 | 「The Takeda Techno-entrepreurship Award 2002, The Takeda Foundation.」 題目「Phytoremediation of heavy metals by polyphosphate-coupled transportengineering.」 |
| 2010年3月20日 | 日本農芸化学会トピックス賞 題目「ホップ(Humulus lupulus L.)におけるリナロール・ネロリドール合成酵素遺伝子の同定」(キリンHD杉村哲らとの共同授賞) |
| 2016年9月2日 | 日本植物細胞分子生物学会(第34回、上田)学術賞受賞。 題目「植物二次代謝の生合成と輸送の統合を目指して」 |
その他
植物生理学会評議員:平成8年~12年(二期)、平成16年~17年度、平成22年~23年度
植物生理学会選挙管理員:平成10年~12年度
Plant Cell Physiology 編集委員:平成16年1月~平成19年12月
Plant Cell Physiology 編集実行委員:平成20年1月~平成23年12月
Plant Biotechnology 編集委員:平成16年1月~平成19年12月
Plant Biotechnology Reports 編集委員:平成22年9月~
植物細胞分子生物学会幹事:平成14年~17年度
「バイオサイエンスとインダストリー」編集委員:平成13年~18年度
日本木材学会編集委員会(J. Wood Sci.):平成15年~18年度
日本農芸化学会関西支部評議員:平成16年~17年度
経済産業省植物プロジェクト研究開発委員:平成18年~22年度
日本植物生理学会庶務幹事:平成20年~21年
日本植物細胞分子生物学会各賞選考委員:平成22~23年度
かずさDNA研究所研究評価委員会産業基盤開発部会委員:平成23年
日本植物生理学会論文賞選考委員:平成20年1月~23年12月(同選考委員長:H23)
日本植物細胞分子生物学会論文賞選考委員:H20年~
科学技術振興機構(JST)日米メタボロミクス共同研究評価委員:H23年度
Scientific Reports, Associate Editor: 平成27年〜令和5年
科学技術振興機構(JST)国際科学技術協力推進委員(SICP):H28年度
日本学術振興会産学協力研究委員会第160委員会委員平成28年~令和2年度
日本学術振興会科学研究費委員会専門員 令和3年〜5年度
NEDO先端研究プログラム研究開発推進委員 平成30年度
バイオインダストリー協会(JBA)植物バイオ研究会 会長 令和2年度〜現在
バイオインダストリー協会(JBA)理事 令和3年〜現在
趣味
スキー、美味しいものを食べること
pagetop