Home People Research Achievement Education Photo Contact
研究室メンバー(2025年度)

教員・スタッフ | ||
| 教授 | 飛松 裕基 | |
| 助教 | 巽 奏 | |
| 特任教授 | 梅澤 俊明 | |
| 特任教授 | 三上 文三 | |
| 研究員 | 山本 千莉(中村正治研 研究員との兼任) | |
| 事務補佐員 | 森 恵 | |
| 事務補佐員 | 奥村 志美 | |
学生 | ||
| 博士3回生 | 高江洲 広司 | |
| 博士3回生 | 土橋フェルナンド諭 | |
| 博士1回生 | 窪井 健斗(JST-SPRING奨学生) | |
| 修士1回生 | Chunxu You(由春煦) | |
| 研究生 | Yanpei Son(孫焱培) | |
| 研究生 | Qianjing Xu(徐乾景) | |
教員プロフィール
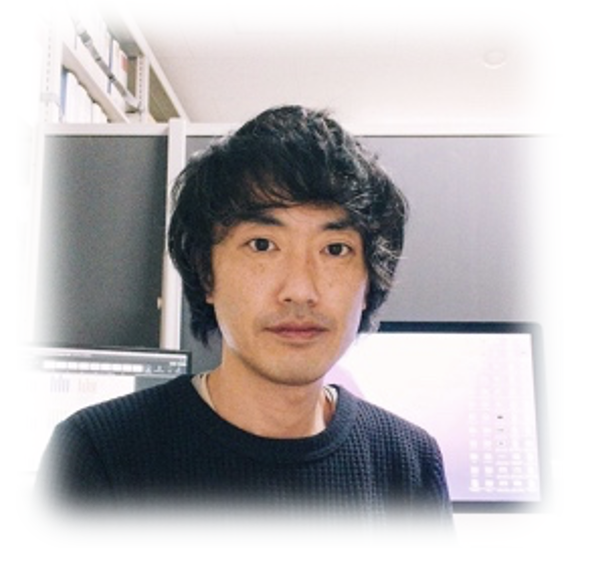
飛松 裕基(教授, 農学博士)
Yuki TOBIMATSU (Professor, Ph.D.)
連絡先
ytobimatsu[at]rish.kyoto-u.ac.jp
([at]を@に置き換えてください)
主な研究テーマ
植物細胞壁(特にリグニン)の構造・生合成・進化・代謝工学
植物バイオマス(特にリグニン)の有用化成品への化学変換・生化学変換
植物二次代謝産物(特にフェニルプロパノイド)の生合成と代謝工学
略歴・研究業績など
SNS

巽 奏(助教, 農学博士)
Kanade TATSUMI (Assistant Professor, Ph.D.)
連絡先
tatsumi.kanade.6v[at]kyoto-u.ac.jp
([at]を@に置き換えてください)
主な研究テーマ
植物細胞外ポリマー(クチン・スベリン・スポロポレニン・リグニン)の生合成
植物細胞外ポリマーの多様性・進化・代謝工学
植物二次代謝産物(特に脂溶性化合物)の輸送
略歴・研究業績など
卒業生(更新中)
教員・スタッフ | ||
| Pingping Ji・研究員(2025年卒;民間企業) | ||
| 坂本正弘・特任教授(2024年卒;民間企業) | 謝冰・研究員(2024年卒;京都大学・助教) | |
| Reza Rival・研究員(2024年卒;インドネシアBRIN・研究員) | Supatmi・研究員(2024年卒;インドネシアBRIN・研究員) | |
| Nie Kai・訪問研究員(2024年卒;中国東華大学・大学院生) | Elodie Lim・訪問研究員(2024年卒;フランスIBMP・大学院生) | |
| 津江直子・技術職員(2023年卒;民間企業) | 荒武・特任准教授(2022年卒;国立遺伝学研究所・研究員) | |
| 尾崎芽久美・技術職員(2022年卒;民間企業) | 志智真由美・技術職員(2022年卒;退職) | |
学生 | ||
| 山本千莉・博士課程(2024年卒;京都大学研究員) | Pingping Ji・博士課程(2024年卒;京都大学研究員) | |
| 窪井健斗・修士課程(2024年卒;博士課程進学) | 小林慶介・博士課程(2024年卒;民間企業) | |
| Osama Afifi・博士課程(2022年卒;ブルックヘブン研究所・研究員) | 高江洲広司・修士課程(2022年卒;博士課程進学) | |
| 土橋フェルナンド・修士課程(2022年卒;博士課程進学) | 寺野真季・修士課程(2022年卒;民間企業) | |
沿革 〜研究室の歴史〜
樋口教授時代(1968-1991)
森林代謝機能化学分野(生存圏研究所)は、木材研究所リグニン化学部門として発足した。初代教授として、カナダ平原地方研究所研究員とフランスグルノーブル大学客員教授をそれぞれ2年および1年勤めたばかりで新進気鋭の樋口隆昌教授が、1968(昭和43)年4月1日に岐阜大学農学部林学科樹木生理化学講座より着任した。また、助教授には木材研究所木材化学部門より佐藤惺講師が着任した。次いで、同年5月16日に山崎徹助手が、同年12月1日に北村晃子助手が着任した。山崎徹助手は同年12月に香川大学農学部へ、北村晃子助手は1971(昭和46)年3月京都薬科大学へそれぞれ転出した。山崎助手の後任として、岐阜大学農学部林学科樹木生理化学講座より島田幹夫助手が1968年11月に、また、北村助手の後任として、中坪文明助手が1971年4月に着任した。さらに、1975(昭和50)年7月に棚橋光彦助手が着任した。大学院農学研究科には林産工学専攻協力講座として参加した。
発足以来1970年代までは、当時未解明のイネ科植物リグニンの化学構造の研究、リグニン生合成酵素系の研究がなされた。 この間、各教官も助手時代、順次海外留学を経験し、生化学や有機化学の先端手法の導入に積極的に取り組んできた。島田助手(米国カリフォルニア大学デービス校[コーン教授]、2年間、米国オレゴン大学院センター[ゴールド教授]、1年間)、中坪助手(米国ハーバード大学[岸教授]、2年間、米国マジソン林産物研究所[カーク博士]、4ヶ月)である。
その後、1981(昭和56)年10月、中坪助手が京都大学農学部林産工学科林産化学講座助教授として転出した。翌年4月梅澤俊明助手が着任し、さらに1984(昭和59)年11月、島田助手が講師に昇任した。その後、1990(平成2)年4月、棚橋助手が岐阜大学農学部助教授として転出した。1970年代後半から樋口教授の停年退官までの約15年間は、リグニンの微生物分解機構解明に関する研究(島田、中坪、梅澤)と木材の化学変換技術(爆砕)(棚橋)に関する研究が集中的に行われた。 なおこの間、梅澤助手は1年2ヶ月間米国バージニア工科大学[ルイス准教授]に留学し、天然物化学・植物代謝化学に関する研究に従事した。
1991(平成3)年3月、樋口教授の停年を迎え、直ちに島田講師が第2代教授に昇任した。樋口教授は、停年退官後1994(平成6)年3月まで日本大学生物資源学部教授を務めた。 樋口教授の在任は22年間に及んだが、この間の業績とりわけ、リグニンの生合成と生分解機構の研究に対し、日本林学会賞、日本農学賞、グルノーブル大学名誉博士学位、米国化学会セルローステキスタイル部門アンセルムペイエン賞、紫綬褒章、日本学士院賞が授与された。さらに、国際木材科学アカデミー会員や、米国科学アカデミー海外会員に選出されるとともに、2000(平成12)年、勲二等瑞宝章が授与された。また、この間、島田助手、中坪助手、棚橋助手、梅澤助手は、それぞれリグニン生合成、リグニンモデル系の開発と微生物分解、リグニンの化学変換及び微生物分解に関する業績で日本木材学会賞を受賞し、島田助手、中坪助手は、国際木材科学アカデミー会員に選ばれた。
島田教授時代(1991-2005)
1991年4月の島田教授昇任後、同月直ちに木材研究所は木質科学研究所に改組された。改組に伴いリグニン化学部門は、生化学制御分野と名称変更し、島田教授、梅澤助手がそのまま在籍、佐藤助教授は古巣木材化学部門が名称変更したバイオマス変換分野の助教授に就いた。次いで、同年6月に服部武文助手が着任した。1993(平成5)年4月梅澤助手が助教授に昇任し、2005(平成17)年3月の島田教授の定年退職までは人事に変動無く3人体制が続いた。この間、服部助手が1年間米国ペンシルバニア州立大学[ティン教授]に、梅澤助教授が8ヶ月間米国ミシガン工科大学[チャン教授]に留学し、それぞれ微生物分子生物学および植物分子生物学の導入を図った。また、梅澤助教授は国際木材科学アカデミー会員に選出されている。なお、1995(平成7)年4月に始まる大学院重点化改組の一環として,1997(平成9)年4月、大学院農学研究科応用生命科学専攻に協力講座として参加し、現在に至っている。
2004(平成16年)4月、木質科学研究所は宙空電波科学研究センターと融合改組され、生存圏研究所となった。この改組に際して、生化学制御分野は森林代謝機能化学分野と名称変更した。翌年3月島田教授は定年退職し、福井工業大学教授に着任した。
島田教授の在任は14年間であったが、この間、木材分解菌の代謝生理(島田、服部)、植物フェニルプロパノイド(特にリグナン及びノルリグナン)代謝の化学(梅澤)に関する研究が主に生化学的及び有機化学的観点から進められたが、徐々に分子生物学的手法の取り込みが進められた。
梅澤教授時代(2005-2023)
2005(平成17)年7月には、島田教授の後任として梅澤助教授が第3代教授に昇任し、現在に至っている。なお、2006(平成18)年4月、生存圏研究所を含む宇治地区4研究所と東南アジア研究所の共同により生存基盤科学研究ユニットが発足した。同ユニットの専任として同年5月、鈴木史朗助教が着任し、梅澤教授および服部助教との連携の下、当研究室にて同ユニットのプロジェクト研究を進めてきた。その後、2010(平成22年)4月鈴木助教は、当分野助教に着任した。また、梅澤教授は2015(平成27)年度同ユニットのユニット長を、また2016~2017年度同ユニットの後継のグローバル生存基盤展開ユニット長を務め、これらのユニットにおける異分野協働プロジェクトの推進に務めた。一方、服部助教は、2011(平成23)年10月、徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部准教授として転出した。次いで、2015(平成27年)3月、京都大学大学院農学研究科森林科学専攻飛松裕基助教が准教授として着任した。また、同年4月山村正臣特任助教が着任した。次いで、鈴木助教は2020(令和2)年2月、岐阜大学応用生物科学部准教授に転出した。山村特任助教は2021(令和3)年11月徳島大学大学院社会産業理工学研究部准教授として転出した。これと前後して、2021年10月~2022年3月の半年間、東京大学大学院生命農学研究科より山﨑清志が特任助教として着任した。
梅澤教授着任後は、広い意味で植物フェニルプロパノイド代謝の化学に関する研究が進められた。特にリグナン及び関連フェニルプロパノイド生合成の立体化学、抗腫瘍性リグナン生合成とともに、リグノセルロースバイオマスの利用特性向上を目指したリグニンの代謝工学研究などが重点的に進められた。特にリグニン代謝工学の社会実装に向けて、インドネシア科学院(現インドネシア研究イノベーション庁)との国際共同研究プロジェクト(JST, JICAのSATREPSプロジェクト)が推進された。また、構造生物学の強化のため、2019(平成31)年5月三上文三京都大学名誉教授(前大学院農学研究科応用生命科学専攻応用構造生物学分野教授)が特任教授として迎えられた。さらに、バイオマスのエネルギー利用・熱分解の強化に向けて、2022(令和4)年4月小西哲之京都大学名誉教授(前エネルギー理工学研究所原子エネルギー研究分野教授)が特任教授として迎えられた。さらに、柴田大輔特任教授(かずさDNA研究所部長、2018年度~2022年度)、荒武特任准教授(元京都大学大学院農学研究科特定准教授、2019年度~2022年度)、花野滋特任講師(元かずさDNA研究所特別研究員、2018年度)が迎えられ、バイオインフォマティクスの強化が図られた。
なお、この間、梅澤教授がイネ科バイオマス植物におけるリグニン代謝工学に関する業績で日本植物バイオテクノロジー学会学術賞を、飛松准教授がリグニンの化学構造解析に関する業績でリグニン学会奨励賞を受賞した。また、飛松准教授は、国際木材科学アカデミー会員に選ばれている。
飛松教授時代(2023-現在)
2023(令和5)年3月の梅澤教授の定年退職にともない、後任として同年4月に飛松准教授が第4代教授に昇任した。三上文三京都大学名誉教授と小西哲之京都大学名誉教授は引き続き特任教授として任用された。また、新たに梅澤俊明京都大学名誉教授が特任教授として任用された。2024(令和6)年3月、巽奏助教が着任した。
2023年3月25日 梅澤俊明 原文作成
2024年3月1日 飛松裕基 更新