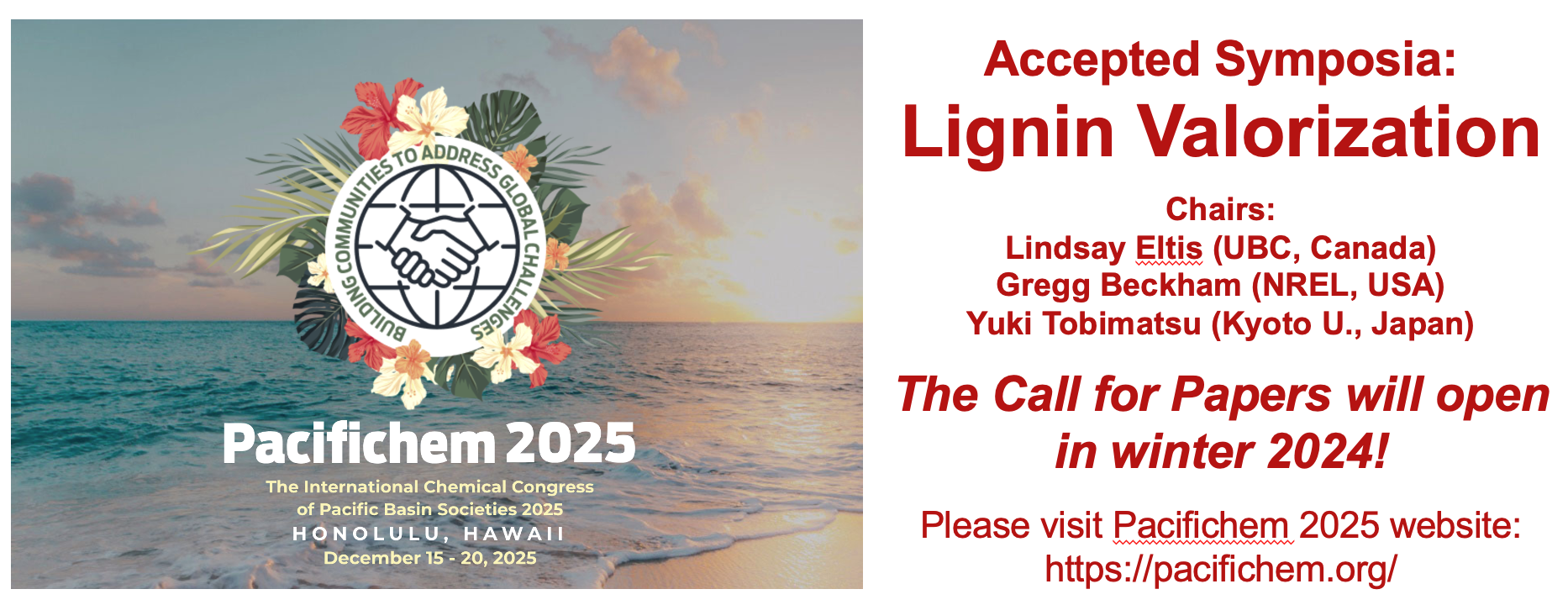Home Member Research Publication Education Photo Contact
NEWS
2025.6.28. Publication
ピンピンさん(研究員)らの論文が New Phytologist に掲載されました!
2025.6.28. Presentation
第7回リグニン学会特別セミナーで飛松教授が講演を行いました。
2025.6.16. Publication
巽助教らの論文が Journal of Plant Research に掲載されました!
2025.6.5. Publication
スパトミさん・ラムさんらの論文が Plant Physiology の News and Views でハイライトされました!
2025.5.2. Publication
徳州学院、青島大学、テネシー大学等との共同研究に関する論文が International Journal of Biological Macromolecules に掲載されました!
2025.4.27. Publication
京大・矢崎研との共同研究に関する論文が The Plant Journal に掲載されました!
2025.4.25. Publication
スパトミさん(研究員)・ラムさん(研究員)らの論文が Plant Physiology に掲載されました!
2025.4.24. Home
2025.4.17. Publication
奈良先端大・吉田聡子研との共同研究の論文(プレプリント)が bioRxiv にポストされました!
2025.4.7. Photo
2025.4.5. Photo
2025.3.31. Member
2025.3.31. Member
研究員の謝冰さんが京都大学大学院農学研究科(高野俊幸研)の助教にご栄転されました。謝さん、2年間、大変ありがとうございました。引き続き、よろしくお願いします!!
2025.3.31. Member
坂本正弘特任教授が退職されました。坂本先生、長い間、大変ありがとうございました!
2025.3.31. Photo
ブリティッシュコロンビア大のShawn Mansfield教授がお招きしてセミナーを開催しました。Shawn先生、ありがとうございました!
2025.3.25. Publication
Pingpingさん(D3)らの論文(プレプリント)を bioRxiv にポストしました!
2025.3.24. Photo
博士及び修士課程(3月卒業)の学位授与式が行われました。おめでとうございます!
2025.3.20. Award
山本千莉さん(D3)の第1回日本木材学会優秀学生賞の授賞式が日本木材学会大会(仙台)で行われました。おめでとうございます!
2025.3.18. Presentation
仙台で開催された国際木材学会及び日本木材学会年次大会に参加し、研究発表を行いました!
2025.3.14. Presentation
金沢で開催された日本植物生理学会年次大会に参加し、研究発表を行いました!
2025.3.4. Publication
木村さん(研究員)の論文が The Plant Journal に掲載されました!
2025.3.2. Publication
木村さん(研究員)の中国科学院CAS・Cui先生、奈良先端大・吉田先生らとの共同研究の論文が Plant Communications に掲載されました!
2025.2.19. Publication
謝さん(研究員)の論文が Journal of Wood Science に掲載されました!
2025.2.12. Presentation
Pingpingさん(D3)の公聴会が行われました。お疲れ様でした!!
2025.2.10. Presentation
2025.2.8. Presentation
日本農芸化学会関西支部例会(@京都大学)で高江洲くん(D2)が発表しました!お疲れ様でした!
2025.1.28. Award
山本千莉さん(D3)が第1回日本木材学会優秀学生賞を受賞されました。おめでとうございます!
2025.1.24. Presentation
TOPICS
場所 京都大学 吉田キャンパス
及び Zoom ハイブリッド開催(研究室見学会は対面のみ)
参加登録 専攻ウェブサイト から事前登録してください。当日参加もOKです。
スケジュールなど詳細は こちら から。

本年度の入試説明会は終了しましたが、個別の相談と研究室見学(オンラインも可)は随時受け付けています。ご希望の方は、こちら からお問い合わせください!!
シンポジウム ”Valorizing Lignin” を開催します!!