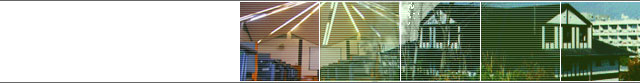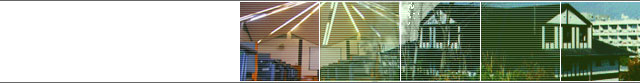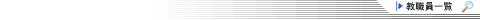
 第126回定例オープンセミナー資料
第126回定例オープンセミナー資料
2010年11月17日
題目
植物細胞培養 —その確立と応用—
Establishment of cell culture system and its application
発表者
荻田信二郎 (富山県立大学工学部生物工学科植物機能工学講座・准教授)
関連ミッション
- ミッション 1 (環境計測・地球再生)
- ミッション 2 (太陽エネルギー変換・利用)
- ミッション 4 (循環型資源・材料開発)
要旨
はじめに
植物は、生殖細胞だけでなくすべての体細胞が、あらゆる組織に分化して植物体を再生し得る能力、すなわち分化全能性(totipotency)を持つといわれている。優良形質を持つ植物のクローンを大量増殖したり、有用な植物代謝物を生産したりできる植物組織培養は、この分化全能性を利用した技術だ。歴史的背景から組織培養事例については、これまで多くの書籍などに解説されている。現在までに、草本植物ではタバコ、シロイヌナズナ、イネ、木本植物ではポプラなど幾つかの種においては、汎用性の高い植物組織培養技術が体系化されている。これらは、植物の複雑な形態形成や生理現象を研究室内で再現できるモデルとして、近年、植物細胞分子生物学の研究分野で広く用いられる。一方で、依然として植物組織培養が困難な植物種も多く、その技術の進歩は植物バイオテクノロジーの発展に必要不可欠だ。本セミナーでは、植物分子細胞生物学に応用される植物組織培養技術について、その中でも細胞培養を中心に系確立と応用に関する議論をしたい。
カルス培養
研究者は、概ね増殖性を指標に植物組織の培養を行い、カルスが誘導できたら、新しい培地にカルスを移植して増殖を促す。増殖したら、再分化を誘導するといった流れになる。一見単純操作のようであるが、注意すべき点は多い。一般にカルスは、移植の量、培養容器の大きさ、光条件、温度条件、培養期間などによってその性質が変化し得るものである。培養変異の問題もある。「成功の秘訣は?」と問われると、「あなたの目的は?」と返答するように努めている。カルスを活用した実験系は実に多彩であるが、研究目的に応じたカルスを選抜することが重要だと考える。演者は、色調の違いに着目して一定期間毎に一定量のカルスを規則正しく移植することによって、特殊な代謝能力や分化能力を発現したカルスを選抜することが多い。
懸濁培養
植物器官あるいはカルスを液体培地で培養することによって、細胞を無限に増殖させるのが懸濁培養(suspension culture)である。これによって得られる懸濁細胞(suspension cell)は、カルスと比べて均質であり、増殖も早いことから、植物生理学や植物分子細胞生物学分野の多くの研究者に利用されている。例えばタバコ BY2 細胞やイネ Oc 細胞などが株化された植物細胞として有名である。詳しくは理研 BRC 実験植物開発室(http://www.brc.riken.go.jp/lab/epd/catalog/pcult.shtml)にアクセスするとよい。
さて、実際に対象植物種のカルスから懸濁培養を行う際には、液体培地中で細胞が遊離するかどうかが問題となる。やわらかく水気に富んだカルスであれば増殖も旺盛であり懸濁細胞を得やすいが、比較的硬いカルスを扱う場合は、あらかじめオーキシンやサイトカイニンの濃度を高くした培地で培養を行い、増殖を促しておくか、セルラーゼなどの細胞壁分解酵素溶液に浸すか、あるいはピンセットなどで物理的に細胞をほぐすなどの前処理が必要となる。ここでも細胞の選抜眼が問われる。
再分化
一旦カルスや懸濁細胞が得られれば、どのように植物体を再生させたい(できる)のかを検討することになる。植物生理学や植物分子細胞生物学分野においては、遺伝子組換えが可能かどうかも重要な点である。一般に不定芽を形成させる方法と不定胚を形成させる方法があるが、ここでは高い分化全能性を発現しており、1 細胞から植物体再生が可能であるというユニークさから、不定胚形成(somatic embryogenesis)について触れておく。
不定胚を形成するという特殊な分化状態を保った細胞、すなわち不定胚形成細胞(embryogenic callus)を介する細胞培養法である。ニンジンなど被子植物の多くは、胚軸や葉から直径 10 から 20 µm の円形小型の細胞を誘導し、そこから球状胚、ハート型胚、魚雷型胚の発達段階を経て植物体に至るとされている。一方、裸子植物であるマツやスギなどの針葉樹では、未成熟あるいは成熟した受精胚から不定胚形成細胞を得る。これらは被子植物の不定胚形成細胞とは異なり、不定胚の本体と伸長した胚柄細胞からなる独特の組織構造をしている。したがって、それぞれの植物種に応じた胚発生様式を把握して研究を進めることが重要だ。
植物細胞培養系の活用
例えば対象植物種の二次代謝系の解明、発生や分化メカニズムの解明、さらには物質の大量生産や異種タンパク質の発現などを目指す研究・開発において、細胞培養は非常に強力なツールとなりえる、と考えている。また、「基礎」や「応用」、何を目指して研究・開発を進めたいのか、研究者の姿勢は十人十色といえる。したがって、1 つのモデル細胞培養系を確立できれば、研究・開発の方向性は無限に広がる(かもしれない)というわけであり、その取り組みは非常に有用である。一方で、同じ植物種、同じ親個体でも、培養細胞株ごとに二次代謝産物の蓄積性などは変化するものであり、このことは、目的遺伝子の発現プロファイルが違う可能性を示している。ここでも目的に応じた細胞の選抜眼が問われることとなる。
|