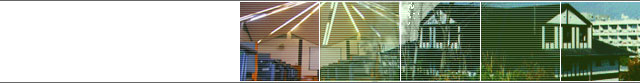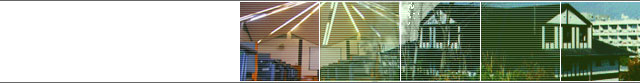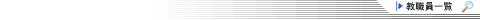
 第44回定例オープンセミナー資料
第44回定例オープンセミナー資料
2006年12月13日
題目
DNA と樹種識別
発表者
馬場啓一 (京都大学生存圏研究所バイオマス形態情報分野・助手)
共同研究者
- 杉山淳司 (京都大学生存圏研究所・教授)
- 大山幹成 (東北大・植物園・助手)
- 高田克彦 (秋田県大・木高研・助教授)
- 反町始 (京都大学生存圏研究所・技術職員)
- 横山操 (京都大学生存圏研究所・ミッション研究員)
関連ミッション
- ミッション 1 (環境計測・地球再生)
- ミッション 4 (循環型資源・材料開発)
要旨
樹木を含む顕花植物の分類では、花の形態が最も重要視され、ついで実、葉などの特徴が用いられる。これは古典的植物分類学の手法である。木材は、樹木の中に蓄積される二次維管束木部の集合体であるという生物学的側面だけでなく、種々の日用品から家具や建造物をつくるための材料として有史以前から人類に用いられ、われわれの生活に密着して存在する身近な材料でもある。従って、木材は樹木を離れて木材だけになった状態で我々が手にする可能性が極めて高く、木材だけしか試料として得られなくとも樹種を識別することは様々な局面で有用な情報となることから、木部の形態的特徴を顕微鏡で観察して樹種識別する手法が発達してきた。ただ、この方法で識別できるのは一般的に属レベルまでで、種の識別までできるものは限られていた。近年、分子生物学とコンピューターの発達によって、DNA に存在するわずかな変異を見出し、比較することが可能になり、分類学の大系が大きく変わろうとしている。基本的には、これまで通り形態的特徴を比較する方法を踏襲しつつも、DNA 変異の報告を加味することによって、被子植物については、1998 年、2003 年と相次いで系統分類体系の見直しが行われた。DNA 変異の研究でスギ科が無くなりヒノキ科に吸収されてしまったことも記憶に新しい。樹種識別の例としては、ブナ科におけるブナとイヌブナを紹介する。ブナ・イヌブナは木材だけでは樹種の識別が不可能であったが、rbcL 遺伝子上に 1 ヶ所の塩基置換が見つかり、樹種を識別することが可能となった。
|