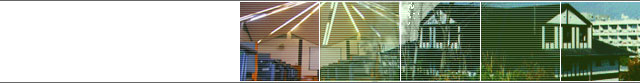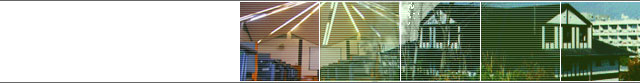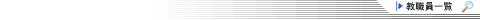
 第34回定例オープンセミナー資料
第34回定例オープンセミナー資料
2006年7月19日
題目
生存圏研究所における先端無線工学からの寄与
—携帯電話のマイクロ波技術の基礎と応用—
発表者
川﨑繁男 (京都大学・客員教授)
共同研究者
- 橋本弘蔵 (生存圏研究所生存圏電波応用分野・教授)
- 篠原真毅 (生存圏研究所生存圏電波応用分野・助教授)
関連ミッション
要旨
生存圏研究所におけるマイクロ波技術の応用は、宇宙太陽発電衛星におけるマイクロ波無線送電である。近年は、このマイクロ波技術を既存の通信機器への無線給電や電気自動車への給電といった応用への展開が始まっている。
もともとマイクロ波技術に代表される無線工学技術は、情報通信とレーダのようなセンサへの適用が主であった。しかし、今日の携帯電話の急速な普及のもとに、マイクロ波デバイス・回路・通信システムが急速に発展してきている。これにともない、自動車のセンサや気象観測、資源探索などのレーダ技術もハイレベルの段階へと進化しつつある。これらの発展は、小型・軽量・多機能システムを実現させた高周波半導体デバイスと集積回路技術が一翼を担っているといっても過言ではない。高周波回路の基礎は、マックスウェルの方程式から導出される波動方程式であり、携帯電話に用いられている小型集積回路の伝送線路は、この波動方程式の簡単な解法から導かれるもので、理論的取り扱いはさほど複雑ではない。ただ、回路も形状・動作が複雑になるとデバイスの非線形性を考慮しないと正確な特性を予測することができなくなり、精度の高いモデルの研究が精力的に行われているのが現状である。
現在、急速に普及した携帯電話は、マイクロ波技術の結晶とも言える産物である。情報を取り扱うデジタル LSI の部分を除くとアンテナと高出力増幅器を除いてモノリシックマイクロ波集積回路 (MMIC) 技術を用いて数ミリ角で実現している。昔、ラジオ少年が電子部品を買ってきて鉱石ラジオを組み上げた時代と、設計・製作法は大きく異なる発展・展開を見せている。
本セミナーでは、半導体デバイスとその集積回路を中心として、先端マイクロ波工学を多方面より紹介する。
|