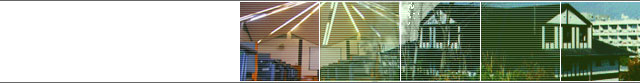 |
|
第7回(2004年第4回)定例オープンセミナー資料2005年1月31日 (その1)題目保存処理木材に由来するホウ素の環境内挙動 発表者中山友栄 (京都大学生存圏研究所・ミッション専攻研究員) 関連ミッション
要旨1) はじめにホウ素化合物は木材保存剤(防虫剤)として使用されている。ホウ素は高い安全性を有するが、処理木材から容易に成分が溶脱するという特徴をもっているので、日本では家具や土台など直接水に接しない場所に主として使われている。しかし、家具などに使用されている処理材の廃棄時には環境への流出が懸念される。しかし、生活圏、森林圏、大気圏を包含した水循環全体をターゲットとするホウ素を含む保存剤中の元素の循環に関する研究はほとんど行われていない。そこで、ホウ素の安定同位体(10B、11B)を指標として用い、環境に存在しているホウ素の起源特定、またホウ素の環境内挙動を把握することを目指している。その第一段階としての目的は、処理薬剤に含まれる有効成分としてのホウ素や処理材中のホウ素、処理された木材から溶脱したホウ素などの、安定同位体比を測定し、各段階でどのような同位体比を有するのかと、いうことを明確にすることである。 2) 研究方法薬剤処理の過程で同位体分別が起こる可能性 スギ(心・辺材)、ベイツガ(心・辺材)、タケ、ゴムノキの試験片(10 (R) × 20 (T) × 50 (L) mm)を用いた。処理薬剤は四ホウ酸ナトリウム(無水)を用い、処理濃度は 1 % Na2B4O7 (ホウ素濃度 0.21 %)で含浸した。四ホウ酸ナトリウム溶液を減圧注入し、その後、処理木材は耐候操作(JIS K1571)を行った。
(1) ICP-MS 試料作製方法
(2) ICP 発光分光分析装置による上記調整試料のホウ素濃度の測定、さらに、ICP-MS (誘導結合プラズマ質量分析計)によるホウ素安定同位体比の測定(1 サンプル 5 回測定)を行った。 3) 現在までの結果
4) 今後の計画薬剤処理過程でのホウ素安定同位体比の測定を行い、処理材およびその溶脱液についても、処理に用いた薬剤の δ11B を保持していることを確認した。そこで、今後は市販の処理材におけるホウ素安定同位体比の測定を行い、生産地域による同位体比の差異、などの検討を行う予定である。 |
