第155回生存圏シンポジウム
第7回伸木会シンポジウム
木質構造に関する最新研究成果発表・討論会
| 開催日時 | 2010/11/17(水曜日) 13:00–17:00 |
|---|---|
| 開催場所 | 京都大学宇治キャンパス おうばくプラザ研修室 1 |
| 主催者 | 京都大学生存圏研究所 伸木会 (木質構造のこれからを考える若手の会) |
| 申請代表者 | 青木謙治 ((独)森林総合研究所・主任研究員) |
| 所内担当者 | 森拓郎 (京都大学生存圏研究所生活圏構造機能分野) |
| 関連ミッション |
ミッション 4 (循環型資源・材料開発) |
| 関連分野 | 建築、木質材料メーカー、木材メーカー、住宅メーカー、設計事務所。 |
目的と具体的な内容
木質材料・木質構造の開発・研究に従事している若手・中堅の研究者及び技術者を対象に、木質構造の種々の性能を読み解くために必要と考えられる最新の研究の成果発表と参加者全員による討論を行う。その議論により、更なる研究の高度化と課題の発掘を目指す事を目的とする。
本シンポジウムでは、3 名の演者を迎えて、現在木質材料や構造の抱える問題の一部分について、ディベートを行った。まず一つ目は、木質構造の接合部における割裂破壊やせん断破壊を明らかにするために必要と考えられる木材の破壊力学についての研究である。ここでは、この分野をうまく構造設計などに活かすために必要な進め方や考え方などについて議論した。二つ目は、釘接合部の劣化について議論をした。評価方法も含め研究の蓄積が少ない分野であるため、様々な検討を進めて行くことで問題点を明確化することの必要性と、長期利用における信頼性確保について議論を行った。最後に、木造住宅の長期利用について必要と考えられるメンテナンスに関する発表を受けて、企業としての考え方や研究者としての視点などについてさまざまな議論がなされた。
生存圏科学の発展や関連コミュニティの形成への貢献
生存圏科学のうち、循環材料や、その利用に関する項目に当たる木質材料・木質構造についての若手のシンポジウムを行った。
次代を担う研究者と学生が、約 5 時間にわたって議論をし、研究者にとっては、新しい研究課題への進展や考え方を得る機会となり、学生にとっては議論の進め方、研究の進め方、そして本質のあるところを学ぶために重要な機会になったと考える。
この様なシンポジウムは、関連コミュニティが発展していくために必要な土台作りになると考える。また、企業の参加により、産官学のつながりを作るためにも多大な貢献をしていると考える。加えて、今後の研究のシーズやニーズについて企業と学際機関の壁を越えて、様々な議論が行われた。これからの分野・所属・地域を超えた新しい共同研究プロジェクト等のあり方についても議論でき、新しいプロジェクトなどの立ち上げに発展することが期待できたと考える。
プログラム
| 13:00–13:10 | 開会挨拶 青木謙治 (森林総合研究所) |
| 13:10–15:20 | (1) 神戸渡 (東京理科大学) 木材の破壊を考慮した構造物設計の可能性 —わかりづらいこと、わかってきたこと— |
| 15:20–15:25 | 休憩 |
| 15:25–17:10 | (2) 石山央樹 (住友林業) 釘接合部の劣化と残存強度 |
| 17:10–17:15 | 休憩 |
| 17:15–17:55 | (3) 田中圭 (大分大学) 柱脚接合部の点検が可能な耐力壁の開発 —2009年度伸木会シンポジウム トステム財団助成の成果— |
| 17:55–18:10 | 総括 青木謙治、森拓郎 |
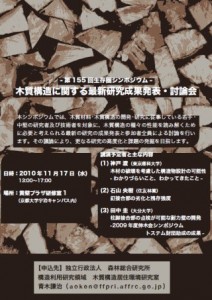 |
ポスター PDF ファイル (4 688 261 バイト) ポスター制作: 元谷文則 |
