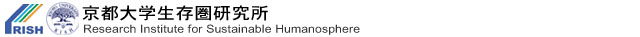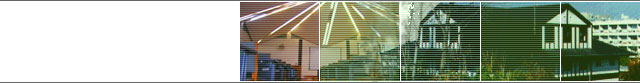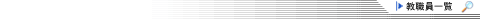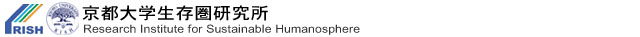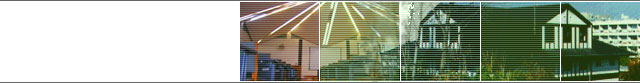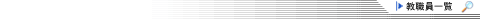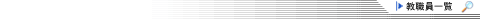
 生存圏研究所 第二回公開講演会 生存圏研究所 第二回公開講演会
1.日時 平成17年10月8日(土)
2.会場 宇治キャンパス 木質ホール3F
入場無料
3.プログラム
1.「宇宙開発・宇宙科学と私たちの暮らし
ーー元気の出る宇宙生存圏開発ーー」 |
教授 松本紘 |
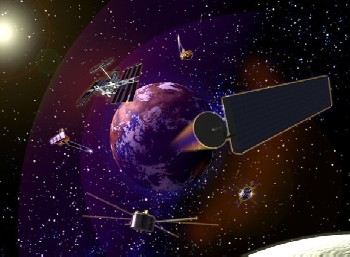 |
20世紀の技術革新に支えられた人類の繁栄は、21世紀の地球社会に「大きなつけ」を
残しました。特に、国土・戦略的資源・エネルギー源に乏しい日本はその影響を強く
受けます。日本の存立基盤を支えるエネルギー・資源安全保障に関わる科学技術政策
として、宇宙科学技術は重要です。「宇宙飛翔体による知的探求の科学」及び「宇宙
開発による実用指向の科学」の現状を踏まえて、これまでの我が国の科学技術政策の
問題点を指摘し、この問題を克服した30年のタイムスパンを視野に入れた宇宙科学技
術の発展の方向性を展望します。 |
| | |
| 2.「人工衛星から見る私たちの生存圏」 |
教授 塩谷雅人 |
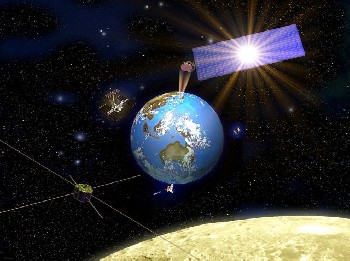 |
人工衛星からの観測は,「神の目」ともいえる俯瞰的な視点で,私たち人類の生存基
盤となる空間(生存圏)をグローバルにとらえることを可能にした.ここでは,さまざ
まな衛星観測の事例にもとづいて,来るべき将来に対する学術的な評価と理解を得る
ための研究基盤について紹介する. |
| | |
| 3.「シロアリと生存圏科学−シロアリは地球を救うか?−」 |
助教授 吉村剛 |
 |
シロアリは木質系住宅の大害虫として悪名が高い。しかしながら、自然界において炭
素や窒素を循環させる非常に大事な虫でもある。生存圏科学という立場から見たシロ
アリ研究の魅力と、その能力を生かした新しい試みについて紹介する |
| | |
| 4.「わが国と中国における木の文化を較べる」 |
教授 伊東隆夫 |
 |
わが国は古来より寺院建築、木彫像など豊富な木質文化財に恵まれている。わが国の
文化のルーツにあたる中国で木の文化の発展はどうだったのでしょうか。遺跡出土製
品、木彫像、古建築などについての比較例を説明する。
|
| | |
|
|