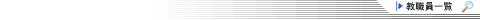
 京都大学生存圏研究所 森林バイオマス評価分析システム共同利用研究内規 京都大学生存圏研究所 森林バイオマス評価分析システム共同利用研究内規
森林バイオマス評価分析システム全国共同利用内規
第 1 条 京都大学生存圏研究所森林バイオマス評価分析システムの共同利用施設の利用については、この内規の定めるところによる。
第 2 条 森林バイオマス評価分析システムは、木質資源の持続的保全・生産ないし活用を目的とした、森林バイオマスの評価分析に関する調査・実験・研究を目的とするものとする。ただし、所長が特に適当と認めた場合は、この限りではない。
第 3 条 森林バイオマス評価分析システムを利用することのできる者は、次のとおりとする。
一 学術研究を目的とする国内外の研究機関に属し、第2条の目的に合致する者
二 教育を目的とする国内外の研究機関に属し、第2条の目的に合致する者
三 民間の企業・団体に所属し、第二条の目的に合致する者(研究代表者とはなれない。)
四 その他、所長が特に適当と認めた者
第 4 条 森林バイオマス評価分析システムを利用しようとする者は、研究代表者を定めたうえ、所定の利用申請書を所長に提出し、その承認を受けなければならない。
第 5 条 森林バイオマス評価分析システムの利用を承認された研究代表者は、森林バイオマス評価分析システムを研究協力者以外に使用させてはならない。
第 6 条 利用者は、承認された利用目的以外の用途に森林バイオマス評価分析システムを使用することはできない。不正利用が確認された場合、所長はその利用を取り消すことがある。この場合、その不正利用に起因するすべての責任は研究代表者に帰属する。
第 7 条 共同利用に伴い明らかな過失または故意により実験・測定機器が故障し、修理の必要が生じた場合は、研究代表者が現状回復することとする。
第 8 条 本学以外の共同利用研究者が研究遂行上受けたいかなる損失及び事故に関しても、応急措置以外、本学は一切の責任は負わず、当該共同利用者の所属機関等で対応するものとする。
第 9 条 研究代表者は、申請書に記載された事項について変更しようとする場合は、研究所が別に定めるところにより、再申請を行うものとする。
第 10 条 研究代表者は、研究終了時に利用結果を所長に報告しなければならない。
第 11 条 所長は、必要に応じて、研究代表者に対して、利用状況・結果の報告を求めることができる。
第 12 条 利用者が森林バイオマス評価分析システムを利用した研究結果を論文等で公表する場合は、京都大学生存圏研究所森林バイオマス評価分析システム (Forest Biomass Analytical System, Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University) を利用した旨を明記するものとする。
第 13 条 森林バイオマス評価分析システムを利用した研究の成果に基づき発明等が生じた場合には、速やかに共同利用専門委員会に通知しなければならない。
2 本共同利用研究の実施により得られる発明等は、原則として京都大学生存圏研究所(以下「甲」という。)もしくは京都大学生存圏研究所に属する研究担当者(研究代表者及び研究協力者)に帰属するものとする。ただし、利用者(前条第 3 条で規定する者で生存圏研究所に属する者を除く。以下「乙」という。)の貢献度に応じて、甲乙間で当該共同利用による成果の帰属とその持分を別途定めることは妨げない。
3 前項の規定に従い本共同利用研究の結果生じた発明等が甲又は乙の単独所有となった場合、当該知的財産権(以下「単独所有に係る知的財産権」という。)は、当該単独所有する者が出願等手続及び権利保全を自らの裁量において行うことができるものとするが、当該発明等に係る知的財産権出願等の前にあらかじめ共同利用研究の相手方の確認を得るものとする。この場合、出願等手続及び権利保全に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
4 第 2 項ただし書の規定に従い本共同利用研究の結果生じた発明等が甲乙間の共有となった場合において、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願契約にしたがって共同して出願等を行うことができるものとする。ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、当該甲又は乙は当該知的財産権を以後自己の単独所有に係る知的財産権として取扱うものとする。
5 第 2 項の規定に従い本共同利用の結果生じた発明等が、甲に属する研究担当者と乙とが共有することとなった場合の当該出願等については、当該甲に属する研究担当者と乙との協議の上、別途定めるものとする。
第 14 条 甲及び乙は、本共同利用の実施にあたり、相手方より開示を受け又は知り得た相手方の一切の情報について、相手方の事前の書面による同意がなければ、これを第三者に開示・漏洩してはならない。
2 甲及び乙は、本条第1項に掲げられる情報に関する資料及び当該情報を保存した媒体等(森林バイオマス評価分析システムを利用する過程及びその結果得られたもの)について適切に管理しなければならない。
3 前 2 項の規定にかかわらず、次条又は次の各号のいずれかに該当する場合は、本条第1項及び第 2 項の規定は適用しない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したことを証明できる情報
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、相手方より開示若しくは提供を受けた本秘密情報を、本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、第 3 条の本共同利用研究を開始した日から研究が完了した日の翌日又は研究を中止した日の翌日から起算して 5 年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
第 15 条 甲及び乙は、本共同利用研究の実施期間中において、共同利用研究の成果を他当事者以外の第三者に知らせようとするときは、少なくとも公表の 2 ヶ月前までに他当事者の承諾を得るものとする。
2 甲及び乙は共同利用研究の実施期間終了後、他当事者に事前に公表の時期、内容、方法等を通知したうえで、共同利用研究の成果を公表するものとする。この場合、他当事者から業務上の支障等により、研究成果を公表しないよう申し入れがあり、甲乙協議が整ったときは、甲及び乙は他当事者の利害に関係ある事項についてその成果を公表しないこととする。
第 16 条 この内規の定めに違反した者、その他森林バイオマス評価分析システムの運営に重大な支障を生ぜしめた者があるとき、所長は利用の承認を取り消し、またはその者に一定期間森林バイオマス評価分析システムの利用を認めないことがある。
第 17 条 この内規に定めるもののほか、森林バイオマス評価分析システムの利用に関し必要な事項は、共同利用専門委員会の議を経て、所長が定める。
附則
この内規は平成 18 年 4 月 1 日から施行する。
もどる
|

